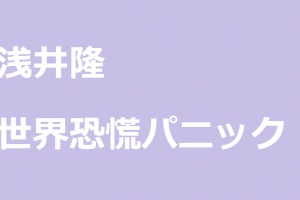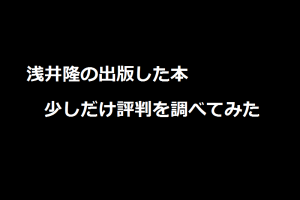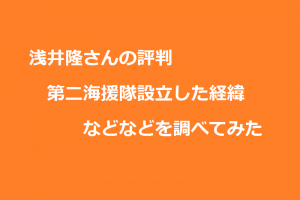日本は破綻する?啓発的な本
浅井隆のこの本もそうですが、彼の書籍の多くは誇張表現が多く、読者は「本当にそうなるの?」という感覚で読める本となっています。
実際に読み物としては楽しめると思っている方も多く、肯定的な意見も多いです。こちらの本でも、日本が破産することを予測して、理論立てているのですが、実際に日本が破綻するかどうかは誰にもわかりません。いつ国債が暴落するかもわかりませんし、経済が機能しなくなるほどの世界恐慌があるかもしれません。今まで多くの本でそれらの予測が語られてきましたが、その予測が当たったことはほとんどありません。たまたま書いていた本と内容が似ていて「当たった」ということはあるでしょう。
しかし、この浅井隆の本はそれらの書籍といったい何が違うのでしょうか。誇張表現によって不安を煽るように見えますが、これは読み物としての特質と言えるでしょう。日本が破産することはおそらく向こう数十年はないかもしれません。しかし、心のどこかで「もしかしたらあるかもしれない」という不安こそ、この本の本質だと言えます。啓発的な面も多く、もしかしたらそういう事態になるかもしれないという点で、論理が展開されているのです。
日本が破綻するかどうかについては、そのときになってみないとわからないというのが実際のところです。ただ、確実にそれに近しいような国家の危機というものは訪れてもおかしくありません。それを彼は文章で表現して、より啓発を促しているのです。いわゆる起こり得る可能性を考えて、それを警鐘として鳴らしている訳です。それこそが、彼の語っている日本の破産の意味です。
予測の信憑性について
こういった不景気を考察・予測するタイプの本が世間に登場し始めたのは、1990年代初期だと言われています。その発端は、かつて日本の経済に巻き起こったバブル崩壊によって、ボロボロな状態に対して、日本経済の破綻・危機という意見が数多く叫ばれていたことでした。
しかし、それでも日本は破綻することなく、経済活動を続けることに成功しました。つまり、いつ破産してもおかしくない状況ではあるものの、そうなる日はいつかわからないのです。そういった予測に対して、「当たっていないのでは」と疑問を持つ方もいるかもしれません。しかし、それは当たり前なのです。今まで出版されてきた人類滅亡論や日本破産論、世界恐慌論などは、その多くが外れています。
しかし、それは、こういった先見の明がある方が考察して、世に発表をして興味を集めたことによって世間にもそういった考え方が認知されたことで最悪のケースを避けてきたという考え方もできるのではないでしょうか。つまりは、この本の伝えたいことは、思考の停止こそが、物事にとって一番よくない形を引き出してしまうということについて警鐘を鳴らしているということです。
浅井隆の考え方が、「起きなかった現実」だと笑われた時こそ、浅井隆の発言が日本にいい影響をもたらしたものだと言えるのではないでしょうか。
破綻論を語ることの意義
近年は浅井隆のように、日本経済の破綻論を語る筆者が多いです。破綻論というのは、常に未来を考察してみて、「もしかしたらこうなる」という内容のものとなっています。
つまり、確実に当たると語ることはできないのです。確かに、その言葉の強さから、極端すぎる予測だとか、あり得ない現実を考えているといった意見もあるかもしれません。それもその通りなのです。
浅井隆の著書の場合は、あえてオーバーな表現を用いて、読者の不安な気持ちを掻き立てるようにしています。不安な気持ちは、人間にとって財産ともいえるような非常に大切な感情です。人間はとても弱い生き物です。他の動物と比べて足が速いわけでもありませんし、空を飛べるわけでもありません。しかし、不安な気持ちによって、事前に起こることを予測することができるのは人間だけです。経済においても、未来を予測して、投資やこの後の経済活動に役立てるというのはとても大切なことです。
日本の破綻論を読んだときに、そうなんだと終わってしまうのではなく、そのうえで万が一日本が破産したとき、どのようになるのかという点を考えておく啓発的な面も捉えると良いでしょう。一つの読み物として「こういう予測もあるのか」と楽しむ程度でも構いません、あくまでもその未来を一度想像することが良いと言えます。
この本では、あえて断定的な表現を使って「こうなる」と予測しています。それは一人の意見にしか過ぎないかもしれません。経済評論家や経済ジャーナリストとして活躍する浅井隆だからこその語り口を、楽しんでみてはいかがでしょうか。もしかしたら本当になるかもしれませんし、ならなくてもそのために準備するきっかけとなれば、この本を読む意義にも繋がってくるはずです。本とは、本来そういう意味合いも強いのかもしれません。まずは読んでみて判断するのも良いでしょう。