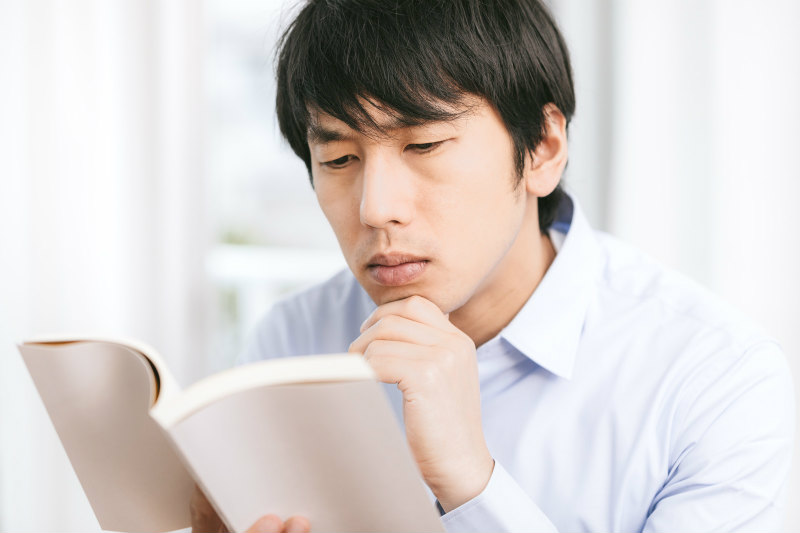第二海援隊の代表を務める浅井隆氏はこれまでに様々な書籍を執筆してきて、その大胆な物言いで話題を呼んでいます。経済評論家という肩書きがある浅井隆氏ですが、実際のところ世界中を旅したり新聞社で働いていた過去があったりと、豊富な人生経験を持つ人としても知られています。そんな浅井隆氏が執筆した「文明と経済の衝突」という書籍について評判などを調べてみましょう。
詩的なタイトル
浅井隆氏にしては珍しく詩的なタイトルが付けられたという印象がまずある本作です。浅井氏と言えばかなり過激とも言える本のタイトルが代名詞のようにもなっている方ですが、今回の「文明と経済の衝突」なんとも詩的な雰囲気のタイトルとなりました。
基本的な流れとしては浅井隆氏が世界経済の過去の歴史とこれからの未来を推察するというものですが、その中で観察されるパターンというものに着目しているのが興味深いところです。この本は初版が1999年と結構前のものなので、この書籍が書かれたあとの世界経済と照らし合わせながら浅井隆氏の述べたことがどのように当てはまったかなどを考えながら読めるので、現在第二海援隊や浅井隆氏に興味を持ち始めている人たちにとっても興味深く読めるものとなっていると思います。
文明と経済の衝突で浅井氏が伝えたいこと
この書籍の中では非常に興味深い歴史に対する浅井氏の考察も見受けられます。歴史をギリシャ帝国の時代や古代ローマ帝国の時代にまでさかのぼり、世界の覇権というものが800年の周期で巡っているという説を展開しています。それぞれの800年の終わりの時期には食料不足が生じ、民族の大移動が起こるという特徴があると唱えています。
そしてここからが投資に興味のある人にとってはとても集中して読みたい部分ですが、歴史的な経済バブルの起こるサイクルについて浅井氏は触れています。そうした経済バブルがほぼ100年ごとに起こっているというのです。有名なチューリップバブルや南海バブルそしてニューヨーク大暴落などを取り上げてこうした100年サイクルを裏付けています。なんだかこうした説を聞いていると映画ウォールストリートで言われていたことを思い出すのは私だけでしょうか。非常に神秘的な部分もあり、世の中の宇宙的な周期というものを感じずにはいられません。
これからの日本経済
浅井氏の主張によればバブルとその崩壊を経験した国が歴代の世界のトップとして君臨してきたという説を唱えているが、日本もバブル崩壊を経験しているので日本が世界のトップとして君臨するときが来るのだろうかという疑問が生じます。しかし浅井氏の推論では日本はそうしたポジションには座ることなく、これからの世界は引き続きアメリカがパワーを保って世界に影響を及ぼしていくという読みになっています。
このように各文明の成り立ちと経済状況、特にバブルの発生とその崩壊のループには深い関係があり、歴史は繰り返すということが読み取れる書籍となっています。普段株上がるか下がるか、儲かったか損したかという観点でしか経済状況や金融情報を見ていない人にとっては、少し時間をとってこうした過去の歴史を落ち着いて考えてみるのも投資脳を育てるのに役立つのではないでしょうか。
この本に対する評判
こうした経済の深い在り方を記した本の場合、読者の好き嫌いがはっきりと出る気がします。この本を読んだ人の評判としては、単純なおすすめ銘柄の話しなどではなく、金融や経済の本質を歴史的に読み解けるので楽しいという意見もあります。特に知識欲が旺盛な人に好評のようで、世界経済や歴史に関する様々な要素を理解しておきたいと思う人には概ね好評のようです。
一方でさっき述べたような「明日の株価の動向が知りたいんだ!」という性格の人にはあまり向かない内容かもしれません。話しが難しすぎるとか、ちょっとオカルトっぽいにおいがするという意見の人もいるようですが、むしろそうした考えの人こそこうした書籍を通して社会の構図や文明と経済の巡り方について考える機会にしてもらえたらいいと思います。
文明と経済の衝突を通して
浅井隆氏の独占インタビューも受けたことのある世界的投資家のジム・ロジャーズ氏も以前に、相場の歴史が繰り返されるものだということを主張していました。やはり世の中には一定のバイオリズムのようなものが存在しているのも事実ですし、人間の集団心理の傾向も同じような出来事を繰り返す要因になっているように感じます。こうした法則が今後当てはまっていくかを見守るのも一つの楽しみになります。
こうした書籍を通して時に深くそうしたことについて熟考することは一つ一つの投資判断をするうえでもとても重要になってくるように思えます。多くの人が稼げるようになる投資本を探していますが、時間を取ってこの文明と経済の衝突のような著書を読んでみると金融相場に対してもバランスのとれた見方が持てるようになるのではないでしょうか。